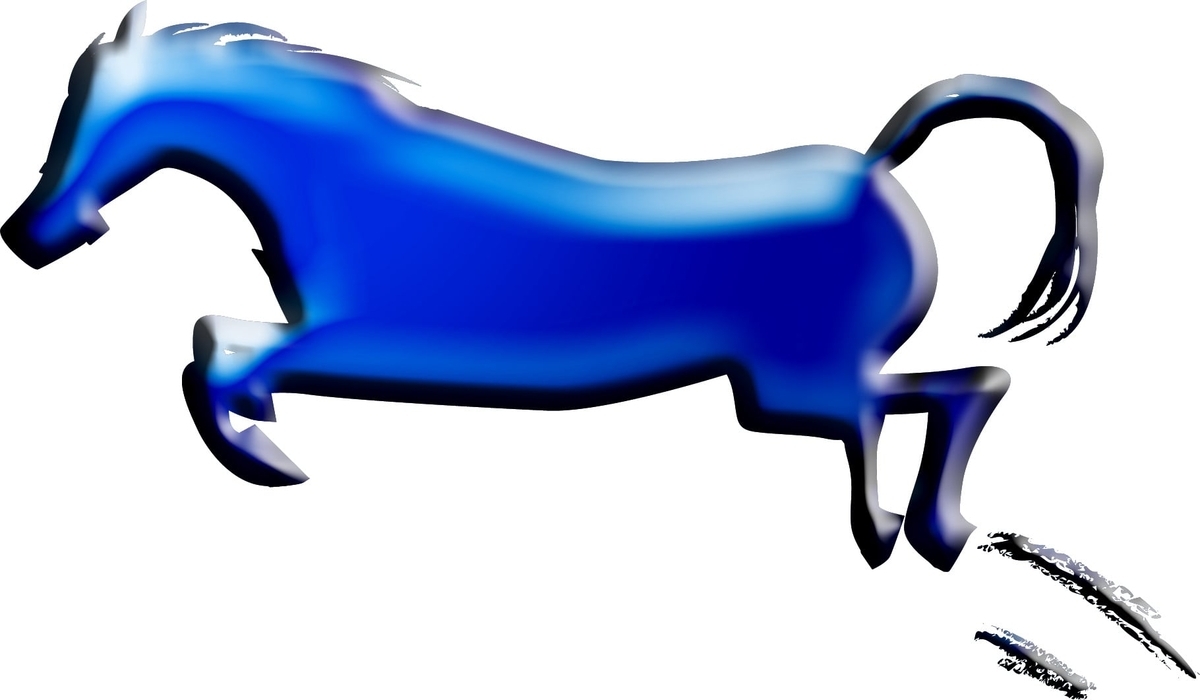
■ブログランキング参加中です(記事が参考になったという方は是非クリックで応援をお願いします)
――レアな瞬発力を試された今年、レベルも悪くなさそうで。
京都新聞杯 2025 レース結果
ホネ的! レース回顧 / レース分析 京都新聞杯 2025
レース全体のふり返り
京都新聞杯 2025 各馬ふり返り 予想と結果
ネブラディスク
予想➡➡➡◎
結果➡➡➡5着
0.6秒差で、時計的にも大したことのない2分15秒台での5着だが、この馬くらいまでは後半水準から重賞でも見直しが可能とみられる悪くはないレベル。
渋って苦にせず、折り合い面からは(脚元を気にして走るほうに集中するなどの作用から)リスク軽減するはずとの見立てでの狙いだったが、この日京都も思ったより渋らず稍重止まりだったのが残念。
本当に渋った馬場をこなすかどうかの確認も含めて、もう少し本格重で見たかったのだが。
その馬場の作用なしだったのでさもありなんといった感じだったが、まあ幼い。
裏を返せば、こういう馬が成長してビタっと折り合うようになった時の爆発力には夢があるが。
ショウヘイ / エムズ / トッピボーン / ナグルファル / キングスコール
勝ったショウヘイは、番手確保から終始馬場の悪いところを避けてのスロー前々Vではあるが、このレースとしてはなかなか優秀な水準での0.4秒差完勝となった。
何と言っても、調教編でも指摘したが今回は「前回は全く走ることができない状態でしたが、今日はとてもいい状態だった。それ通りの走りさえできれば、というところ」と鞍上が振り返った状態面が大きかったのだろう。
あとは、高速決着に対する裏付けがないので、ハイラップの高速馬場で時計対応ができるかなどが未知の部分が鍵に。
スローからのヨーイドンで、決着タイムが遅くなれば、ダービーでも好走は可能なところにいる一頭だと思われるが。
2着エムズは、ラストの直線で「あそこしか無かったんかなー」という進路取りになって(ラチ沿い)もいて、もう少し上振れしてもいいレースをしての連対圏なので上々。
2馬身半差離されたが、今日のショウヘイとの差はもう少し詰まっていい。
4着トッピボーンに関しては、序盤と終盤に折り合いに苦労する面が見られた点が敗因だろう。
ラストは、外から3着デルアヴァーらと同じような競馬をして、一応上り最速はマークしたが、この展開なので折り合いに気を遣って出していけない状態になっては厳しかった。
ただ、力んでの消耗が無ければこの上り33.8秒が、本来もう少し速いものを出せていたとみることが出来る点は、やはり重賞級を示した格好だろう。
前走がハイラップの好時計戦だったため、ともすれば先々への期待は勝ち馬より大きい存在だが。
ほかでは、ナグルファル(6着)も、ハナに立って掛かってしまっていたので論外。
素質は重賞通用級とみられるのでまた改めて。
またここは、渋った馬場を抜きにしても「やってみなければ」な距離耐性の部分からピンかパーで見積もっていたキングスコール(9着)は、最内枠から後方に収まってしまい、3コーナー過ぎからの後半4F45.2秒の高速ラップに付いていくのが精一杯という形に。
ここで追走に脚を使った結果として、2200mを走り切ることはできなかった。
後方、スローからの上り高速化、2200mは「?」、といった3要素から、この大敗は仕方なかった印象。
恐らく、(こなせる可能性は全然ある)2200m以上を使ってくることもなくなる可能性が高く、そうなると休み明けの距離短縮とかで迎えることになる次が真価の場面となるのではないだろうか。